- トップ
- ジャーナル
- 猫の病気と健康のお話
- 猫の下痢の原因や便の異常に早く気づくためのポイント、受診の目安を解説【獣医師監修】
猫の下痢の原因や便の異常に早く気づくためのポイント、受診の目安を解説【獣医師監修】

猫の下痢は一過性の消化不良から感染症による命に関わる深刻な病気まで、さまざまな原因で起こります。野良猫や保護したばかりの猫では、今までの生活環境が理由で下痢を起こしている場合もあり、他の猫に感染を広げないための注意が必要です。
この記事では、猫の下痢の主な原因や異常便の種類、受診の目安、家庭でのケア方法を獣医師がわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
猫の正常な便の回数や状態

猫の排便回数は1日1回程度が一般的です。ただし個体差があり、2日に1回でも便が正常な形と硬さであれば問題はありません。
猫の正常な便は、円柱状で手で持てるくらいの硬さが目安です。色は茶〜こげ茶色で、フードの種類によって多少の濃淡はあります。
毛が混ざるのは問題ない
猫は日常的に毛づくろいをするため、飲み込んだ毛が便に混ざって排出されることがあります。便に少量の毛が混じる程度なら特に心配はいりません。
急性下痢と慢性下痢

猫の下痢は、続いている期間によって「急性下痢」と「慢性下痢」に分けられます。
急性下痢
下痢が始まってから2週間以内の場合をいいます。多くは一過性で、整腸剤や駆虫薬、輸液などの対症療法で回復するケースが多いです。
主な原因
- 急なフード変更や消化不良
- 寄生虫感染
- ウイルス感染
- 誤食や中毒
慢性下痢
下痢が2週間以上続く場合をいいます。背景に病気が隠れている可能性が高いです。動物病院で検査を受け、原因を特定して治療につなげることが重要です。
主な原因
- 内臓の疾患
- 代謝性・内分泌系の疾患
異常便の種類

猫の下痢には様々な種類があり、便の状態で病気の原因をある程度絞り込むことができます。ここでは、異常な便の状態を解説します。
- 軟便
- 水様性下痢
- 黒色便(タール便)
- 鮮血便
- 粘液便
軟便
軽度な消化不良や食事の影響で見られることが多いですが、続く場合は食物アレルギーや慢性疾患が関与していることもあります。
水様性下痢
水のような便で、猫砂に吸収されて大きな水っぽい塊になります。短時間で脱水に陥る危険があり注意が必要です。
黒色便(タール便)
胃や小腸など上部消化管からの出血が考えられます。
鮮血便
大腸や直腸からの出血で、便の表面に鮮血が付着します。
粘液便
便にゼリー状の粘液が混じったり、表面がぬるぬるして見えます。猫砂に透明〜黄白色のネバネバしたものがついていることもあります。
下痢の原因として考えられる病気と治療法
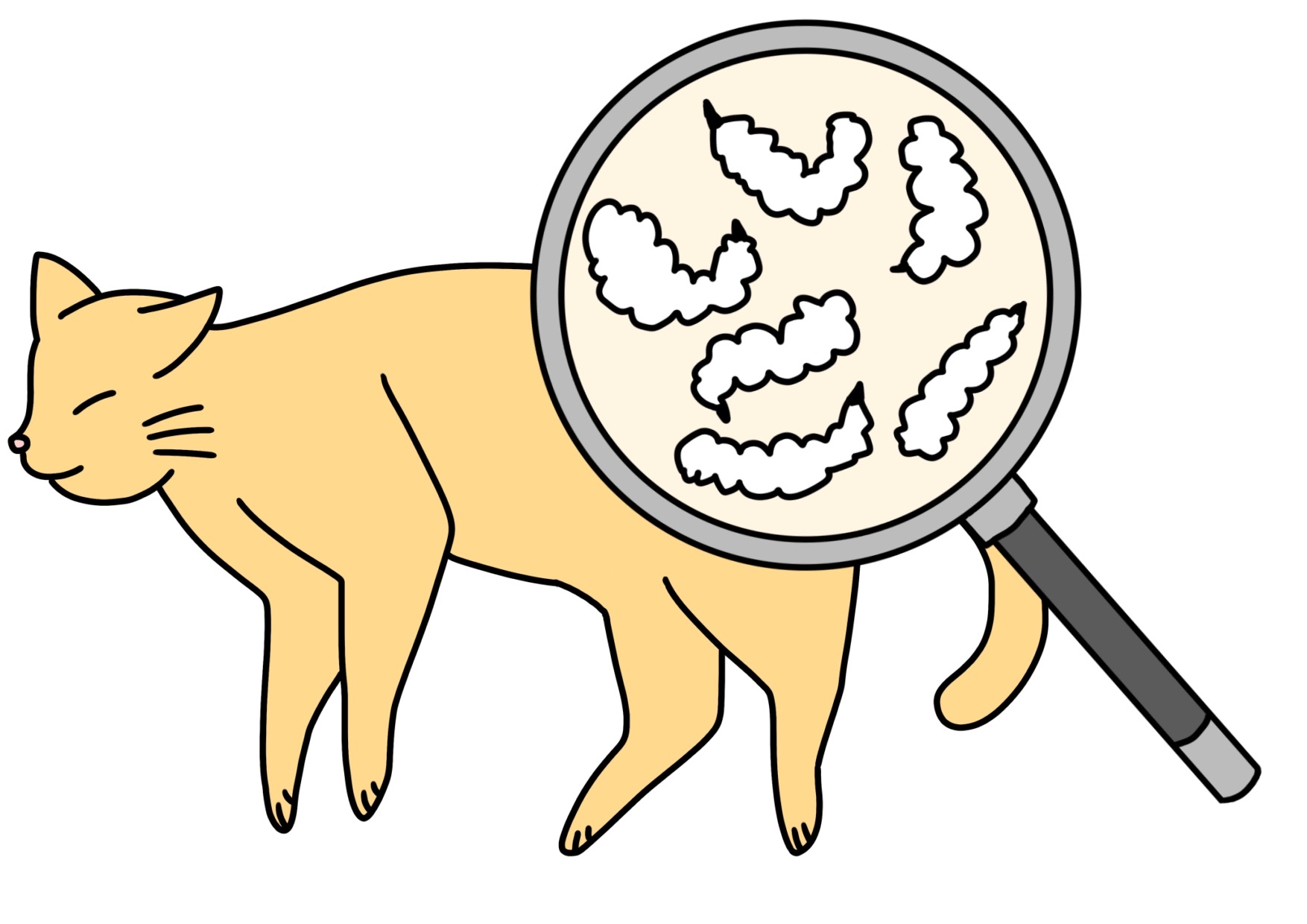
猫の下痢の代表的な原因を分野ごとに整理し、それぞれの治療法を解説します。
- 消化器系の病気
- 消化管以外の内臓の病気
- 細菌やウイルス、寄生虫による感染症
- 食事によるもの
- 代謝性・内分泌系の病気
消化器系の病気
下痢は主に小腸や大腸での吸収障害によって起こるため、腸の病気を取り上げます。
炎症性腸疾患(IBD)
猫の慢性下痢の代表的な病気で、腸粘膜に炎症が起こります。慢性的な軟便や下痢、嘔吐、体重の減少を伴い、長期的な管理が必要です。
治療はステロイドや免疫抑制剤を投与し、腸の炎症をコントロールします。
消化管リンパ腫
シニア猫に多く発生する腫瘍で、下痢や嘔吐、体重の減少を引き起こします。確定診断には、内視鏡や生検が必要です。治療は抗がん剤が中心ですが、腫瘍のタイプや猫の年齢、体力に応じて方法を選びます。
腸閉塞(誤食など)
異物のせいで消化管が詰まり、嘔吐や水様便、血便を伴うことがあります。自然に排出されない場合は、緊急手術が必要です。
消化管以外の内臓の病気
消化を助ける膵臓や肝臓の働きが弱ると、栄養をうまく吸収できず下痢につながることがあります。
慢性膵炎
膵臓に炎症があると消化酵素がうまく分泌されず消化不良を起こし、下痢や軟便につながります。嘔吐や食欲不振、体重の減少を伴うこともあります。慢性膵炎に続発して、膵外分泌不全が起こることがあります。
治療は、膵臓への負担を減らした食事や、輸液などで症状の回復を図ります。
慢性腎不全
加齢により腎臓の機能が低下することが原因で、多くのシニア猫が発症する病気です。腎臓の機能低下が直接的に下痢を起こすことは少ないですが、進行すると食欲不振や消化不良から便の異常を起こすことがあります。
細菌やウイルス、寄生虫による感染症
猫の下痢の原因には、感染症も多く含まれます。特に子猫や保護したばかりの猫では重症化しやすく、早期の診断と治療が大切です。
猫汎白血球減少症
猫パルボウイルスによる重い感染症です。子猫に多く、激しい下痢や嘔吐を起こし命に関わることがあります。ワクチン接種で予防できるので、必ず接種しましょう。
猫コロナウイルス感染症
多頭飼育環境で広がりやすいですが、多くの猫は軽い下痢や軟便で回復します。まれに、体内でウイルスが変異すると猫伝染性腹膜炎(FIP)に移行し、命に関わることがあります。
寄生虫感染(ジアルジア、コクシジウム、トリコモナスなど)
保護猫や外出する猫、多頭飼育の環境では今でも寄生虫感染がよくみられ、粘液便や水様便、血便といった症状が現れます。寄生虫ごとに駆虫薬が違うため、動物病院での糞便検査と診断が欠かせません。
細菌感染
サルモネラやカンピロバクターなどの細菌感染でも下痢が起こります。発熱や嘔吐を伴うことがあり、人にうつる可能性もあるため、早めの受診と衛生管理が大切です。治療は抗生剤を投与します。
食事によるもの
猫の下痢の原因には、食事の与え方や内容が関わっていることも多いです。
急なフード変更
猫は人よりも消化の適応能力が低いため、急にフードを変えると腸内環境が乱れ、下痢を起こすことがあります。フードの切り替えは少しずつ行いましょう。
食物アレルギー
特定のタンパク質に対して免疫が反応し、下痢や嘔吐、皮膚のかゆみなどを引き起こします。診断や治療は獣医師の指示に従いましょう。
誤食・中毒
ネギ類の野菜、チョコレート、薬などの誤食で下痢や嘔吐、中毒症状が出ることがあります。
代謝性・内分泌系の病気
代謝やホルモンの分泌異常が下痢に結びつくこともあります。
甲状腺機能亢進症
中高齢の猫に多い病気です。主な症状は体重減少や多食ですが、腸の動きが活発になりすぎて軟便や下痢を伴うこともあります。治療は内服が中心です。
受診の目安

猫が下痢をしたとき、自宅の様子見でよいケースと、受診すべきケースをまとめました。
1〜2日様子を見てもよいケース
- 下痢以外の体調不良がない
- 元気・食欲がある
- 水分がしっかりとれている
受診すべきケース
- 元気や食欲がなくぐったりしている
- 繰り返し嘔吐や下痢をしている
- 下痢が水のようで止まらない、または血が混じっている
- 半日以上水分をとらない、尿量が極端に少ない
- 子猫・高齢猫・持病のある猫
動物病院での検査方法
動物病院では、便を直接もしくは顕微鏡を使って観察したり、感染症を疑うときは遺伝子検査を行ったりして原因を突き止め、治療を行います。
猫が下痢のときの過ごし方

猫が下痢をしたとき、家庭でどのように過ごさせるかは回復に大きく影響します。猫は犬と比べて絶食や環境変化に弱いため注意しましょう。ポイントは、以下の4点です。
- 下痢に早く気づいてあげる
- 食事は消化に良いものを
- トイレを清潔に
- 安静に過ごさせる
①下痢に早く気づいてあげる
猫は便を砂で覆い隠す習性があるため、下痢や血便などの異常に気づくのが遅れることがあります。
猫の下痢を早く発見するためには、
- 猫砂の塊の大きさや形
- トイレ周囲の汚れ
- トイレ以外の場所での排便がないか
- 便のにおいの変化
などを普段から観察し、異常があれば早く対応しましょう。
②食事は消化に良いものを与え、水分補給はしっかり
軽い下痢でも元気や食欲があれば、消化にやさしいフードを少量ずつ与えましょう。下痢のときは水分と電解質が失われるため、水はしっかり与えましょう。
水をあまり飲みたがらないときは、ウェットフードやお湯でふやかしたフードを利用すると水分摂取量を増やせます。
③トイレを清潔に
猫はきれい好きなので、トイレが汚れていると排泄を我慢してしまう子もいます。下痢のときは特に汚れが残りやすいので、砂をこまめに交換しトイレを清潔に保ちましょう。
多頭飼育では普段からトイレを分けるのが理想ですが、感染症のときは特に排泄物の処理に注意しましょう。
④安静に過ごさせる
猫は基本的には室内飼育なので運動制限は不要ですが、ストレスの少ない静かな環境で休ませることが回復につながります。来客や大きな音などの刺激は避けましょう。
野良猫・保護してすぐの猫の下痢に注意

野良猫や保護したばかりの猫は、ワクチン接種も受けていない上に、生活環境や食事の内容がわからず、寄生虫や感染症にかかっていることも少なくありません。
今までは残飯や獲ったネズミなどを食べていたのに、急にキャットフードに切り替わることで消化不良を起こす猫もいます。また、環境の変化でストレスを感じ、一時的な下痢になることもあります。
人や他の猫への感染を防ぐためにも、猫を保護したらまず動物病院で健康診断を受け、下痢がある場合は早期の対応をおすすめします。
まとめ
猫の下痢には食事やストレスといった一過性の原因もあれば、感染症や腫瘍など重大な病気が隠れていることもあります。
普段から便やトイレの状態をよく観察し、異常が続いたり下痢以外にも他の症状がある場合は、早めに動物病院を受診しましょう。飼い主の早い気づきと適切な対応が、猫の健康を守る大切なポイントです。
【執筆・監修】
獣医師:安家 望美
大学卒業後、公務員の獣医師として家畜防疫関連の機関に入職。家畜の健康管理や伝染病の検査などの業務に従事。育児に専念するため退職し、現在はライターとしてペットや育児に関する記事を執筆中。
おすすめ記事
 2025.03.12
2025.03.12「保護猫と歩む、私の新しい一歩」オキエイコさんインタビュー
保護猫の迎え方や保護猫活動の多様さを、飼い主目線で描いたコミックエッセイ『ねこ活はじめました かわいい!愛しい!だから知っておきたい保護猫のトリセツ』の著者・オキエイコさん。 発売から4年が経ち、世の中ではずいぶん「保護 […]
 2025.02.17
2025.02.17保護猫活動の現場から—保護猫団体「ゆらり」代表・山岡りえさん インタビュー
「いつも通りに、猫と生きる」 いよいよスタートした保護猫支援プロジェクト「ピースニャンコ」。活動の主軸のひとつは、連携している保護猫ボランティアへの医療費支援だ。 猫のためにともに活動する仲間たちという想いを込めて、ピー […]

カテゴリー
人気ランキング

野良猫は冬をどう生きる?寒さ対策と私たちにできることを解説
寒さが厳しくなる季節、外で暮らす野良猫たちはどのように冬を乗り切っているのでしょうか。この記事では、野良猫が冬をどのように過ごしているのか、その実態と私たちにできるサポートについてご紹介します。 野良猫は冬をどう過ごして […]

「猫バンバン」の正しいやり方は?車と小さな命を守るためにできること
寒さが厳しくなると、温かい飲み物や暖房が恋しくなるのは人間だけではありません。外で暮らす猫たちにとっても、冬の寒さは命に関わる厳しい問題です。そんなとき、暖を求めて猫たちが入り込んでしまう場所の一つが、私たちの身近にある […]

「猫の種類は数あれど」キジトラ編
「キジトラ」といえば、茶色をベースにした黒縞模様。日本でもよく見かける猫の毛柄です。実はこのキジトラ、ただ身近な存在というだけでなく、猫の祖先の姿を最も色濃く残した毛柄でもあるのです。なぜキジトラはこんなに馴染み深いのか […]

野良猫への餌やりは違法?気を付けるべきポイントや猫を救うための活動を紹介
町で痩せた野良猫を見かけると、「お腹が空いているのかな?」「仲良くなりたい」と思ってしまうことがあると思います。しかし、正しい方法で行わなければ、近隣住民とのトラブルや猫の繁殖問題が生じることもあるため、この記事では餌や […]

野良猫の鳴き声がうるさくて困っている方必見!対策や根本的解決法を紹介!
夜中に「アオーン」「ニャオーン」と鳴き続ける野良猫の声で、眠れない夜を過ごしていませんか?特に春から夏にかけての季節、窓を開けて寝たい時期に限って野良猫の鳴き声が響き、仕事や学校に影響が出るような睡眠不足に悩まされること […]






















