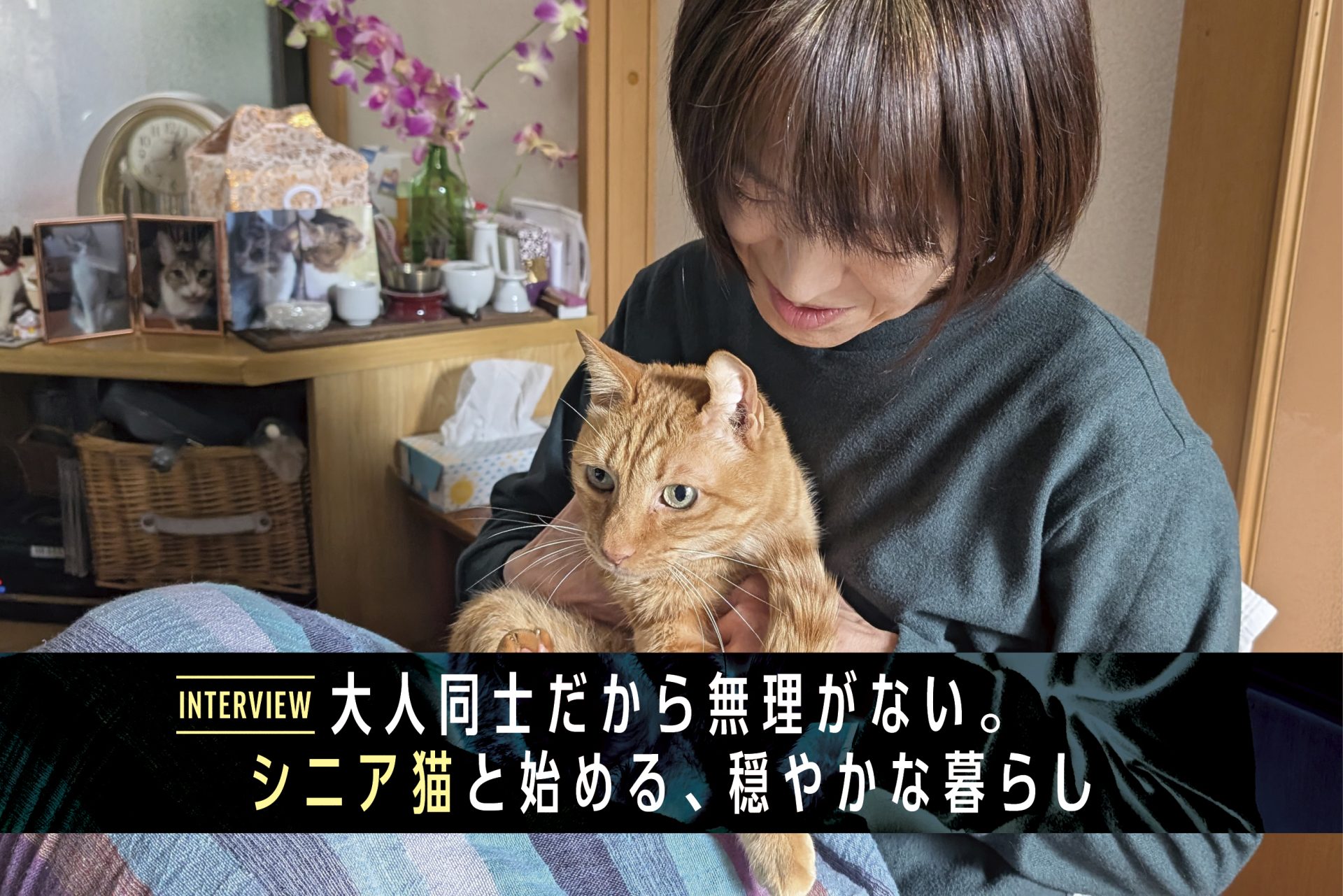「保護猫が、研究者を生んだ。」ネコ心理学者・髙木佐保先生インタビュー
人間と暮らす身近な動物のひとつでありながら、イヌに比べるとまだまだ謎が多い、ネコの心。
飼い主なら日々の暮らしで実感しているさまざまな能力も、これまで科学的には証明されていなかった。そこで立ち上がったのが、ネコ心理学者の髙木佐保先生をはじめとする、ネコ研究者たち。
彼らはCAMP NYAN TOKYO(キャンプ ニャン トウキョウ)というチームを結成し、ネコの心についての研究に日々取り組んでいる。おかげで私たちは、少しずつ愛すべき隣人の心を知れるようになってきた。

そんなネコを愛する髙木先生がこの道に進んだきっかけは、1匹の保護猫だった
初めて飼ったネコに背中を押されて
大学で心理学を学ぶ中で、「比較認知科学(ヒトを含む様々な動物の認知能力を比較することで、心の機能の進化を解明する学問)」と出会った髙木先生。幼い頃から動物の気持ちを知りたいと思っていた彼女は、動物研究にのめりこむ。
修士・博士課程では、比較認知科学を研究する京都大学・藤田和生先生の研究室に所属。ちょうどその前後で、築約100年の実家にネズミが出没したため、ネコを飼うことに。
「それが生後2か月で迎えた女の子『ミル』。初めて動物を飼ったので、本当にかわいくて。保護猫という存在は以前から知っていましたし、個性的で唯一無二の魅力を持つ雑種のネコが大好きで、保護猫団体から迎えました」
他の動物も研究対象にしていた髙木先生だが、ネコの自由奔放さに魅了され、研究の主軸はいつしかネコへ。そして実家を離れて神奈川に引っ越した2019年、「ネコがいない生活なんて無理!」と、新たに2匹飼い始める。
「今度は男の子を飼ってみたいと思って、『みかげ』と『くらま』という兄弟を迎えました。その子たちも保護猫出身ですね。でも飼い始めてみたら全然性格が違って。ミルは小さいのに自立心が強くてやんちゃ。みかげとくらまは穏やかで、『あ、ネコってこんなに温厚なんだ……』と驚きました(笑)」
ネコの心を科学する研究チーム

CAMP NYAN TOKYOは、京都大学CAMPの東京支部。この「CAMP」という言葉は、Companion Animal Mind Projectのこと。イヌやネコをはじめとする伴侶動物=コンパニオンアニマルの心を調査しているプロジェクトチームだ。
伴侶動物の研究には、一般の飼い主&飼いネコたちの調査協力が必要になるが、大学の研究室単位で募集してもなかなか難しい。そこで研究室の垣根を越えてチームを組み、集約した窓口を作ったのだ。
「私たちの研究は飼い主さんからの応募によって成り立っているので、より協力していただきやすい形を目指してこの形になりました。短時間で済む調査もあるため、チームでご家庭に伺い、複数の調査を行うこともあります」
研究調査にはどんな性格のネコも大歓迎

イヌのように研究室に連れてきて調査をしようにも、知らない場所は警戒するのがネコというもの。調査は各家庭を訪問して行う形が基本だ。しかし協力するには、やはり人懐っこいネコのほうが良いのだろうか?
「いえいえ、どんな子でもOKです。隠れてしまっても、カメラさえ設置できれば対応できる調査もありますし、偏りのないデータのためにも、さまざまなネコちゃんに参加してもらいたいですね。調査は長くても2時間くらい。お互い疲れちゃうので、もっと早く終わることもあります」
ノウハウが蓄積されたことで、どういう実験ならネコも楽しんで参加できるのかわかってきた。髙木先生も調査を重ねるうち、「うちの子がこんなに、知らない人の前に来るなんて」と言われることが増えてきたのだとか。
「ネコちゃんに警戒心を与えない動きが、だんだん身についてきたのかもしれません(笑)」
曖昧なことを、ひとつずつ確かめていく

ネコの認知機能の中でも、“言葉の理解”に興味があるという髙木先生。たとえば、同居猫や飼い主の名前を認識しているのかという研究を行い、「ネコは同居猫や飼い主の“名前”も“顔”も認識している」ことが証明された。
「ネコの飼い主さんたちは『そうだと思ってた』という反応でしたが(笑)、私は結構懐疑的だったんです。研究者なので基本的に疑う姿勢というのも理由ですが、みかげとくらまが一緒にいるとき、片方の名前を呼ぶと2匹とも振り向くので、わかっていないのでは?と」
日々の暮らしでは曖昧なことも、きちんと実験で確かめると“わかる”――そこに研究の面白さがあると、髙木先生は語る。コツコツと小石を積むような、地道で緻密な営みは、並々ならぬ熱意がなければ続かない。
ネコも日本語と別の言語を聞き分けている?

「最近は『ネコは日本語と別の言語の違いがわかるか』を調べています。私たちは、何語かわからなくても『日本語かどうか』はわかりますよね。音の高低やリズムなどの特徴を知っていれば、何語かの推測もできる。そういう能力がネコちゃんにも備わってるのかなと」
そういえば我が家の子どもたちは、それまで楽しんで観ていた英語番組も、3~4歳頃からは嫌がるようになっていた。あれは日本語と他の言語の特徴を捉えられるようになってきたから?
「まさにその年頃から、言語全体の特徴を捉えだすんですよ。子どもの発達と動物の心理の研究は、本当に近い領域なので、すごく参考になりますね」
実際、この調査は乳幼児と同じ手法を使うのだそう。まず日本語以外の言語と日本語を聞かせた時に反応が異なるのかを調べている。こんなふうに髙木先生の実験は、“視覚”より“聴覚”が優れているネコの特徴を大事にして考えられている。
保護猫からもらった学びと、ネコ尽くしの日常

保護猫を迎えたことが縁で、ネコ心理学者となった髙木先生。調査に協力してくれるネコたちにも、保護猫は多いのだそう。
「保護猫活動のおかげで、うちのかわいい3匹に会えたわけですから、活動されている方々には頭が上がりません」
研究でもネコと会い、常にネコのことを考え、家に帰ればネコが待っている。ネコ尽くしの暮らしを送る髙木先生のお話は、その端々からネコへの愛が溢れている。……たまに、ネコに飽きるようなことはないのだろうか?
「それは無いですね。ネコのかわいさはピカイチですから!それに、研究で会うよそのネコちゃんとうちの子というのは、全然違います。よそのネコちゃんには『こうしたら怒っちゃうかな?』とか、気を遣いますからね。自分のネコなら何をしたら怒るかもわかっているので、気兼ねなく付き合えます(笑)。
ありきたりな言葉ですが、私はネコの自由気ままさが好きで、憧れます。私もネコのように、他人の顔色ばかり窺うのではなく、自分のやりたいことを大事にして生きていきたいんです」
ネコを“わかる”ことで、より良い社会に

では最後に。ネコ心理の研究によって、ネコと人間の関係がどうなってほしいと思いますか?
「少子化の時代でペットが増え、中でも一番飼育数が多いのがネコ。人間に一番近い動物を理解することは、今後ますます求められていくんじゃないでしょうか。一緒に住んでいるのにどんな生きものなのかわからないと、不適切飼育にも繋がりかねないと思うんです。
たとえば人間はコミュニケーションに特化した生きものですが、イヌは群れで狩りをする生きものだし、ネコは単独のハンターという生きもの。その能力や気質というのは、かなり根強く残っています」
だから擬人化して扱わないように心掛けています。その言葉は、多くのドッグトレーナーやイヌ研究者からも聞いた警句と同じ。一緒に暮らす“家族”だけど、人間とは違うと忘れないことが大切だ、と。
「よく理解していないと『これくらいわかるでしょ!』とイライラして、問題行動の原因を作ってしまいかねない。だから、科学的にネコの心を解き明かすことで飼い主さんの理解が深まり、良好なコミュニケーションが生まれ、ネコちゃんと飼い主さんのQOLが高まることを願っています」
番外編 うちの子の“気持ち”が知りたい!

ピースニャンコのスタッフから寄せられた質問の中から、いくつかを厳選して髙木先生にお答えいただきました。
Q.フードの好き嫌いが激しく、すぐに飽きてしまいます。なぜ?
A.同じフードが続くと他のものが食べたくなるというのは、心理学的にも説明はつきます。あとネコはイヌに比べて、ちょこちょこ食べをしますよね。イヌと比べて食欲が薄い傾向があるので、よけいに食欲をかき立てる要素が必要になるのかもしれません。ネコの食について研究している先生もいますので、今後さらにわかってくると思います。
Q.「寝るよ~」と声をかけるとベッドに来てくれます。人間の言葉がわかってる?
A.ネコはルーティンを覚えますし、状況を読む力が優れているので、時間帯や服装といった全体的な状況を見ているのではないでしょうか。動物病院に行くとき、すぐ察して隠れてしまいませんか?私もいつも苦戦していますが(笑)、あれがネコの状況を読む力なんです。
Q.犬とネコとで、最適な環境は違いますか?
A.そもそも“最適な環境”の定義が、イヌもネコも研究途上なんです。ただ、ネコのほうが家具を上り下りしたりできる分、快適な場所を自分で見つけるのが得意なので、ワンちゃんをより気に掛けてあげるといいのかなと思います。
取材・執筆 熊倉久枝
編集者、ライター。編集プロダクションを経て、2011年よりフリー。インタビュー記事を中心に、雑誌、WEBメディア、会報誌、パンフレットと多様な媒体の企画編集・ライティングに携わる。ペットメディア歴は、10年以上。演劇、映画、アニメ、教育などのジャンルでも活動。
おすすめ記事
 2025.03.12
2025.03.12「保護猫と歩む、私の新しい一歩」オキエイコさんインタビュー
保護猫の迎え方や保護猫活動の多様さを、飼い主目線で描いたコミックエッセイ『ねこ活はじめました かわいい!愛しい!だから知っておきたい保護猫のトリセツ』の著者・オキエイコさん。 発売から4年が経ち、世の中ではずいぶん「保護 […]
 2025.02.17
2025.02.17保護猫活動の現場から—保護猫団体「ゆらり」代表・山岡りえさん インタビュー
「いつも通りに、猫と生きる」 いよいよスタートした保護猫支援プロジェクト「ピースニャンコ」。活動の主軸のひとつは、連携している保護猫ボランティアへの医療費支援だ。 猫のためにともに活動する仲間たちという想いを込めて、ピー […]

カテゴリー
人気ランキング

野良猫は冬をどう生きる?寒さ対策と私たちにできることを解説
寒さが厳しくなる季節、外で暮らす野良猫たちはどのように冬を乗り切っているのでしょうか。この記事では、野良猫が冬をどのように過ごしているのか、その実態と私たちにできるサポートについてご紹介します。 野良猫は冬をどう過ごして […]

「猫バンバン」の正しいやり方は?車と小さな命を守るためにできること
寒さが厳しくなると、温かい飲み物や暖房が恋しくなるのは人間だけではありません。外で暮らす猫たちにとっても、冬の寒さは命に関わる厳しい問題です。そんなとき、暖を求めて猫たちが入り込んでしまう場所の一つが、私たちの身近にある […]

「猫の種類は数あれど」キジトラ編
「キジトラ」といえば、茶色をベースにした黒縞模様。日本でもよく見かける猫の毛柄です。実はこのキジトラ、ただ身近な存在というだけでなく、猫の祖先の姿を最も色濃く残した毛柄でもあるのです。なぜキジトラはこんなに馴染み深いのか […]

野良猫への餌やりは違法?気を付けるべきポイントや猫を救うための活動を紹介
町で痩せた野良猫を見かけると、「お腹が空いているのかな?」「仲良くなりたい」と思ってしまうことがあると思います。しかし、正しい方法で行わなければ、近隣住民とのトラブルや猫の繁殖問題が生じることもあるため、この記事では餌や […]

野良猫の鳴き声がうるさくて困っている方必見!対策や根本的解決法を紹介!
夜中に「アオーン」「ニャオーン」と鳴き続ける野良猫の声で、眠れない夜を過ごしていませんか?特に春から夏にかけての季節、窓を開けて寝たい時期に限って野良猫の鳴き声が響き、仕事や学校に影響が出るような睡眠不足に悩まされること […]